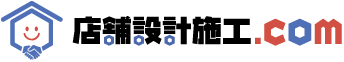投稿日:/最終更新日:
この記事は約3分で読めます
記事の監修・執筆者:古川原

自宅でカフェやサロンなどを営業する自宅兼店舗は、通勤や家賃などさまざまなメリットがある一方で、注意すべきポイントも多数あります。
そこで本記事では自宅兼店舗の開業のポイントをご紹介。メリット・デメリットや、間取りの注意点などをまとめました。ぜひ参考にしてください。
店舗設計施工.com
自宅兼店舗の3つのメリット
自宅兼店舗(店舗兼住宅)とは、ひとつの建物の中に居住スペースと店舗スペースがあり、両者を自由に行き来できる構造の物件を指します。
これに対し店舗併用住宅は、居住スペースと店舗スペースがひとつの建物内にある点は共通していますが、それぞれが独立していて行き来ができないのが特徴です。
自宅兼店舗には主に次のようなメリットがあります。
テナント料がかからない
自宅で店舗を開業する最大のメリットは、テナント料が不要になることです。
一般的に店舗を賃貸で借りる場合、月々のテナント料に加えて保証金・礼金・仲介手数料など多くの初期費用が発生します。しかし、自宅兼店舗であればこうしたコストを大幅に抑えることができます。特に開業当初は売り上げも少なくテナント料が大きな負担になりますが、自宅兼店舗ならその心配がないでしょう。
また、一定の条件を満たせば事業用ローンを住宅ローンと一本化できるケースもあります。住宅ローンは一般的に金利が低く設定されていますので、資金調達の面でも大きなメリットといえます。
通勤時間がかからない
自宅兼店舗は、通勤時間が不要になる点も大きなメリットです。
店舗が自宅と一体になっているため、出勤や移動の手間がなく、その時間を営業や家事などにあてることができます。

限られた時間を有効に使えるため、副業としての店舗運営や、家事や育児の合間に営業するといった柔軟な働き方が可能です。特にワンオペレーションで営業する個人事業主の方や、小さなお子さんのいるご家庭にはメリットとなるでしょう。
仕事と生活が両立しやすい
たとえば小さなお子さんがいる場合、通常であれば保育施設や預け先を探す必要がありますが、自宅で開業する場合はお子さんの様子を見守りながら営業することも可能です。
また、自宅なら深夜や早朝などの時間帯も柔軟に活用できるため、生活スタイルに合わせて店舗の運営が行え、家事や育児との両立もしやすくなります。
自宅兼店舗のデメリット
自宅兼店舗にはデメリットもあります。あらかじめデメリットを知っておくことで、自宅兼店舗の開業で失敗するのを防ぐことができます。
プライバシーの確保が難しい
店舗スペースと居住スペースが隣接しているため、来客や通行人の視線が気になったり、喋り声などの騒音がうるさく感じたりする場合があります。
また、逆に生活音が店舗側に漏れてしまう場合もあります。これらを予防するには、間取りや動線の工夫、仕切りの設計などが重要になります。
セキュリティを厳重にする必要がある
自宅兼店舗は不特定多数の人が出入りするため、セキュリティ面への配慮が欠かせません。防犯カメラの設置や、居住スペースの施錠を徹底するなど、防犯対策を万全にしておきましょう。
店舗と住居の境界を明確に分けることも、防犯性を高める上で重要なポイントになります。
建築や法規の制限がある
用地地域によっては、自宅兼店舗として建てられる建物の面積や営業できる業態に制限が設けられているため、希望する店舗・業態での開業が難しいケースがあります。
設計の段階で建築士や行政などに相談し、法規上の不備や認識のズレがないかをしっかり確認しておくことが大切です。
駐車場や近隣関係の問題
住宅エリアに店舗を出す場合、お客様用の駐車スペースを確保しておく必要があります。また、近隣の方に迷惑をかける可能性がないか事前に確認しておくことも、開業後のトラブルを防ぐための重要なポイントです。
騒音や車の出入り、看板の設置などについても配慮しておきましょう。

集客が難しい場合がある
たとえば駅前などの商業エリアに比べて、自宅兼店舗がある住宅エリアは人通りが少なく、集客に工夫が必要になることがあります。
開業前からチラシを配布したり、SNSを活用して情報発信するなど、効果的な宣伝活動を行っておくことが大切です。まずは地域の方に知ってもらうきっかけを作ることで、リピーターの獲得にもつながります。
自宅兼店舗の開業で失敗しないポイント
自宅兼店舗の開業前に確認しておきたいポイントをご紹介します。
用途地域を確認する
自宅兼店舗を開業する前に、まず自宅のあるエリアの用途地域を調べます。日本の国土は都市計画によって、建てていい建物が決められています。特に住居系エリアの場合、第一種低層住居専用地域では厳しい制限がありますので、ご注意ください。
用途地域は自治体の窓口で尋ねるか、下記の「用途地域マップ」でも調べることができます。
参考:用途地域マップ
第一種低層住居専用地域は10mまたは12mまでの低層住宅のための地域で、原則として店舗は建築できませんが、一定規模以下の店舗兼住宅であれば建築が可能です。
条件:店舗部分の床面積が50㎡以下、かつ延床面積の2分の1未満であること。
第一種低層住居専用地域内に建築することができる兼用住宅
- 事務所(汚物運搬用自動車、危険物運搬用自動車その他これらに類する自動車で国土交通大臣の指定するもののための駐車施設を同一敷地内に設けて業務を運営するものを除く。)
- 日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店
- 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗
- 洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗(原動機を使用する場合にあつては、その出力の合計が0.75kW以下のものに限る。)
- 自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75kW以下のものに限る。)
- 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設
- 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75kW以下のものに限る。)
第二種低層住宅専用地域も主に低層住宅専用地域ですが、一定の条件を満たせば店舗の建築が可能です。
条件:2階以下で延べ床面積が150㎡以下の小規模な店舗であること。
第二種低層住居専用地域内に建築することができる店舗、飲食店等の建築物
- 日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店
- 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗
- 洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗で作業場の床面積の合計が五十平方メートル以内のもの
- 自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもので作業場の床面積の合計が五十平方メートル以内のもの
- 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設
店舗と生活の動線を分ける
自宅と店舗が同じ建物内にあるため、店舗と生活の動線をしっかり分けることが大切です。
お客様からの視認性を高めるため、店舗スペースは原則1階に配置するのがおすすめです。1階を店舗、2階を居住スペースと分けることでプライバシーの保護やセキュリティ強化も実現できます。
住宅入り口と店舗用入り口を別々に設け、トイレも分けましょう。ただし、第一種低層住居専用地域内に建築する場合は、建物内で店舗と住居スペースを行き来できることが条件になりますので注意が必要です。
近隣住民に配慮する
住宅エリアで店舗を営業する際には、近隣住民への配慮がとても大切です。来客による路上駐車を避けるために専用の駐車スペースを確保する、人の出入りや物音が気になりやすい早朝や夜間の営業は控えるなど、近隣住民の日常生活の妨げにならないような工夫が必要です。
また開業前に近隣の方へご挨拶や説明を営業内容について行っておくことも、良好な関係作りを行う上で有効です。
集客方法を工夫する
住宅エリアで開業することは、商業エリアと比べて立地や集客力の面で不利になりがちです。自宅兼店舗の集客力を高めるためにはさまざまな工夫が必要です。
- 外観やエクステリアは人目を引くデザインにする
- 外から店内が見えるような設計にする
- SNSに「地域名+ジャンル」のハッシュタグをつけて投稿する
- Googleのビジネスプロフィールを活用する
- 来店されたお客様に特典を用意して口コミや紹介を促す
- 周辺地域へのチラシ配布、ポスターの掲示
- 通りから見える場所にのぼり・看板の設置
- イベントやワークショップを開いて地域の人を呼び込むきっかけを作る
まとめ
自宅兼住宅は、費用や時間の面でメリットが多い一方、生活空間との区別やセキュリティ、集客などの面で問題があります。また、暮らしやすさと働きやすさのバランスを考えながら、将来のライフスタイルの変化も見据えた設計が重要です。
自宅兼店舗の開業で後悔しないためには、計画段階から専門家に相談することがおすすめです。自宅兼店舗の開業について相談できる業者をお探しの方は、当サイトの無料相談フォームをご利用ください。
店舗設計施工.com
記事の監修・執筆者
-
株式会社ライフワン 古川原
保有資格:
・2級建築士/
・第2種電気工事士/
・一般建築物石綿含有建材調査者/
・石綿作業主任者
店舗設計施工.com運営担当の古川原です。施主様、店舗デザイン・内装工事・建築工事会社様にも満足いただけるよう皆様をサポートさせていただきます。
コラムでは皆様の出店・開業に役立つ情報を発信していますので、当マッチングサービス内容も併せてぜひご覧ください!